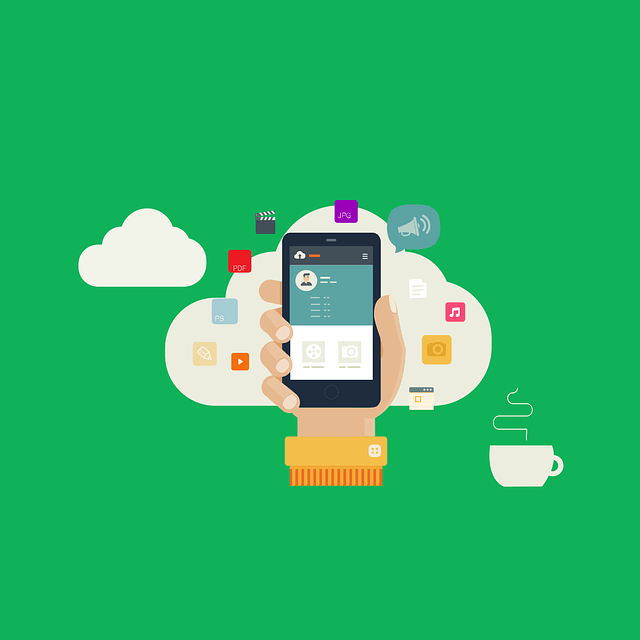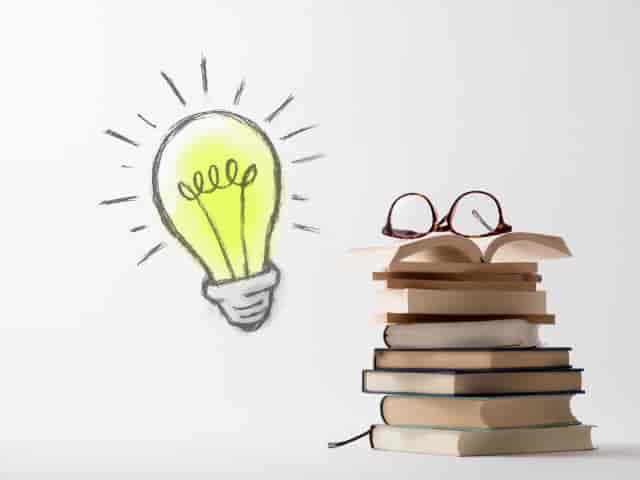本記事では、ネットワークの基本設計書の項目を整理しております。
これから基本設計書を作成される方は、ぜひご覧ください!
>>参考記事: 「【まとめ】ネットワークエンジニアがよく利用するCiscoサイト(ツール)一覧」
>>参考記事: 「無線LANのトラブルを少なく!提案・基本設計時に考慮すべきこと!」
>>参考記事: 「CCIEが語る!ネットワークエンジニアにオススメな本・参考書!」
以下が、基本設計書の目次案です。
以降の内容は、基本設計書の目次に沿って、1つずつご紹介いたします。
【まず最初に】更新履歴 を入れよう!

まずは、更新履歴欄を作成しましょう。
基本設計書はお客様とのやり取りの中で頻繁に更新されることが一般的です。
そのため、更新履歴を記載しておくことは、資料の整合性を保つために非常に重要です。
例えば、バージョン、日付、更新内容、更新者、承認者を明記することで、後から変更履歴を確認しやすくなります。
以下は、一般的な更新履歴の一例です。
| Ver | 日付 | 更新内容 | 更新者 | 承認者 |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2020/12/1 | 初版 | △△ | 〇〇 |
| 0.2 | 2020/12/10 | 3-1. ルーティングプロトコル(OSPF)の選定理由 更新 | △△ | 〇〇 |
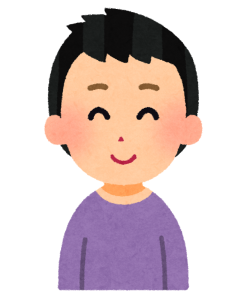
お客様からの最終承認が得られた時点でバージョン1.0になるように、それまでは0.1などの小数点付きのバージョンを使用しましょう。
基本設計書 第1章:概要

第一章「概要」では、案件概要の部分を中心に記載いたします。
本案件の詳細を知らないエンジニアでも、本章を見れば案件の全体像を把握できるように簡潔かつ明確にまとめることが重要です。
主な項目は以下の通りです。
- 本書の目的
- 用語の定義
- スコープの定義
第1章:概要 ① 本書の目的
本項目では、基本設計書の目的や役割を記載します。
案件の内容を簡潔に要約する形で記述すると、関係者が理解しやすくなります。
本書は〇〇様の△△ネットワーク構築に関する設計内容を記載したものである。
〜(以降は案件に応じた内容を記載)
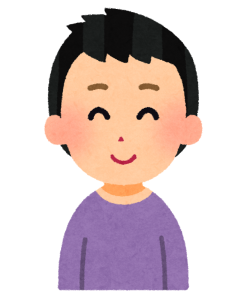
基本設計書は案件の引き継ぎ(後任・運用チーム)の時に、重宝されます。
ネットワーク導入の経緯やその利用目的も明記しておくことで、より案件引き継ぎがスムーズに行えるようになります。
第1章:概要 ② 用語の定義
次に、基本設計書で使用される案件固有の用語を定義します。
基本設計書を他のエンジニアが読んだ際にも理解できるよう、特にお客様の業務システム名などの独自用語は整理しておくことが重要です。
具体的には、以下のような内容を表でまとめておきましょう。
- 本基本設計書に記載されるお客様独自用語 (業務システム名、チーム名、WAN名、機器名称など)
- 本基本設計書に記載される自社独自用語 (業務システム名、チーム名など)
- 本基本設計書に記載されるITサービス名 (SaaSなど)
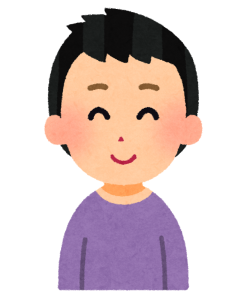
本案件の関係外のエンジニアが「この用語ってどういう意味」っと聞かれないように、しましょう!
第1章:概要 ③ スコープ定義
次に基本設計書のスコープ範囲を記載します。
ネットワーク関連の案件ではネットワーク概略図を掲載し、お客様ネットワーク全体の中での本ネットワークの位置づけや、他ネットワークとの接続関係を簡潔にまとめます。
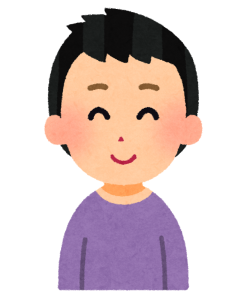
ネットワークの詳細な内容は第2章「物理設計」以降で取り扱うため、この章では簡略版で問題ありません。
そして、お客様ネットワーク全体の中でこの基本設計書で取り扱う範囲(スコープ)を明確に記載しておきます。
特に顧客との責任分界点(責任区分)を明確にし、本基本設計書の位置付けとスコープをはっきりさせることが重要です。
もし、スコープ外の範囲については別の基本設計書で整理されている場合は、その基本設計書の名称を記載しておくと良いでしょう。
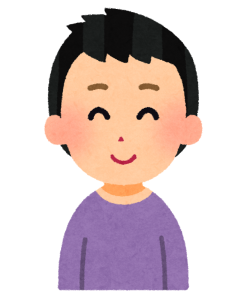
それぞれの設計書との関連性を示すことで、後の作業者が理解しやすくなります!
基本設計書 第2章:物理設計

第2章「物理設計」では、本ネットワークの物理的な設計部分を詳細に記載します。
機器の物理配置や接続方法など、ネットワークの物理的な構成要素を明確にします。
第2章「物理設計」の主な項目は以下の通りです。
- 物理構成図(概要)
- 機器一覧
- 物理配線設計
- ポート収容設計
- 設備/電源設計
第2章:物理設計 ① 物理構成図
物理構成図を掲載し、全体のネットワーク構成(物理面)を表現します。
この構成図は、ネットワーク機器の物理的な配置や接続関係を簡潔に示したものです。
なお、基本設計書では設計コンセプトが分かる程度の概要構成図のみ掲載し、細かい物理構成図は「別紙」管理にした方が保守性が高まります。
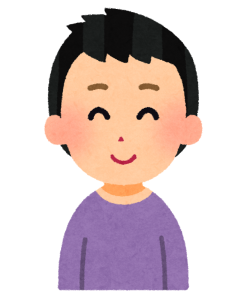
詳細な物理構成図は「別紙_物理構成図」として別途管理しましょう。
この詳細版は運用フェーズにおいてネットワーク機器の追加や変更が生じた際に更新されることが多いため、基本設計書の本文内に含めるのではなく、別紙で管理することがおすすめです!
第2章:物理設計 ② 機器一覧
この項目ではネットワークで導入予定の機器一覧とそれぞれの選定理由を記載します。
機器の選定理由の要素としては、以下の項目が一般的です。
- 必要な機能が備わっているか(お客様の要件を満たす機能)
- 必要な性能を持っているか(期待されるパフォーマンスやスケーラビリティを提供できるか)
- コスト(予算に見合ったコストパフォーマンスがあるか)
なお、詳細なスペック(機器諸元)は、基本設計書の本文ではなく付録(Appendix)として整理する方が見やすくわかりやすいです。
第2章:物理設計 ③ 物理配線設計
次にネットワーク内で使用するケーブルについて、整理します。
この項目では②機器一覧で記載した機器同士をどの種類のケーブルを使って接続するか?をまとめます。
なお、物理構成図と同じように、設計コンセプトが分かる程度のみ掲載し、細かい配線図は「別紙」管理にした方が保守性が高まります。
基本設計書の本文上では、以下のような項目を整理し記載しましょう。
- どの機器とどの機器を接続するのか?
- メタルケーブル(ストレートやクロス)・光ケーブル(シングルモードやマルチモード)どちらを使うのか?
- ケーブルの色分け方針は?
- ケーブルタグの記載方針は?
最低限、上記の項目を表などを使って整理しましょう。
そして、運用時・次回のネットワークリプレース時に混乱が生じないように、できるだけ選定理由も記載しておきましょう。
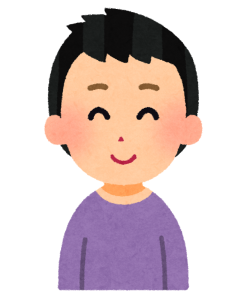
ケーブルの種類によって利用可能な帯域や距離が異なるため、適切なケーブルを選定することが重要です。
また、ケーブルの色分けやタグ付けも明確にして、運用時に混乱が生じないようにしましょう!
第2章:物理設計 ④ ポート収容設計
この項目では各ネットワーク機器のポートの使用順序や規則について記載します。
以下のような項目を整理し記載しましょう。
- ダウンリンク向けポートの使用順序 (例:○番ポートから昇順で使用など)
- アップリンク向けポートの使用順序 (例:○番ポートを使用など)
- 現地作業用の保守ポート (○番ポートを利用など)
- ミラー用ポート (○番ポートを利用など)
- PoE(Power over Ethernet)給電可能ポート (電力供給上限を考慮)
- 冗長リンク向けポートの使用順序
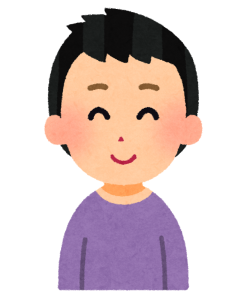
リングアグリゲーション機能にてリンク冗長をする際、チップ単位(ASICやFIYなど)で冗長設計設計することで、信頼性を向上させることができます。
シングルポイントを最低限になるように設計しましょう!
なお、ポート収容設計の項目では、各メーカが無料公開している機器の画像データを使って、図で分かりやすくまとめましょう。
例>Ciscoの場合(Cisco ステンシル)
https://www.cisco.com/c/en/us/about/brand-center/network-topology-icons.html
別記事でステンシルなど、各メーカで提供している便利サイトを紹介しておりますので、興味のある方はご覧ください。
>>参考記事: 「【まとめ】ネットワークエンジニアがよく利用するCiscoサイト一覧」
>>参考記事: 「【まとめ】ネットワークエンジニアがよく利用するJuniperサイト一覧」
第2章:物理設計 ⑤ 設備/電源設計
この項目では、設備設計・電源設計に関する内容と整理します。
主にネットワーク機器を設置するオフィス・データセンタに関する物理情報やラック情報などを整理します。
なお、物理構成図と同じように、設計コンセプトが分かる程度のみ掲載し、細かいラック搭載図は「別紙」管理にした方が保守性が高まります。
以下のような項目を整理し記載しましょう。
- ネットワーク機器を設置する拠点の住所・フロア情報
- ラックの位置や型番情報
- ネットワーク機器の収容規則
- パッチパネルの搭載ポリシーや収容規則
- 冷却・エアフロー設計 (ネットワーク機器の吸気・排気など)
- 拠点の電源状況・仕様
- ネットワーク機器ごとの電源設計 (電源系統をA系/B系で分けるなど)
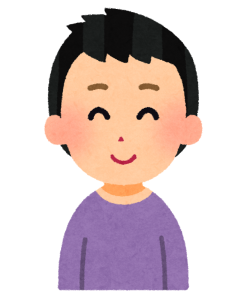
重要な拠点(データセンターなど)では、電源系統の設計もしっかりとやりましょう!
また、お客様のご要望によっては物理セキュリティ設計も求められるケースがありますので、必要に応じて追加しましょう。
論理設計

設計方針
まず最初に論理設計の大方針を定義します。
論理構成図
論理構成図(概要図)を記載いたします。
物理構成図と同様、論理構成図(詳細版)は、「別紙_論理構成図」を作成し管理しましょう。
ホスト名 命名規則
導入機器のホスト名の命名規則を定義します。
保守運用時に発生する新規ネットワーク機器の増設などを見据えて、命名規則を考えましょう。
※例 [お客様略称]-[拠点コード][用途(WAN / CORE等)][機器番号]
L2設計
以下よりL2テクノロジー関連の設計を記載します。
※保守運用時に実施する新規ネットワーク機器の増設時に再設計/再検討がないように設計ポリシーを決めましょう。
VLAN設計
VLANの採番方針、VLAN名称規則、用途を定義します。
- VLANは用途毎にレンジを予約しましょう。(例>業務VLANは1〜100、音声VLANは1〜10、運用VLANは200等)
ポート設計
L2ポートのポート種別(Access or Trunk)、ポート設定(Speed/Duplex,MDI,DTP)、設定値の根拠の設計方針を定義します。
※各ポートの設定は別紙_パラメータシートを作成し管理しましょう。
- 利用用途毎にポートの設定パターンを定義しましょう。(例>業務VLANはAccessポート、Auto/Auto等)
L2ループ設計
L2ループ設計(リンクアグリゲーション, VTP, STP, RSTP, MST, Stack等)の設計方針、設定値、設定値の根拠を記載します。
STPに関する記事は以下に纏めておりますので、ご興味のある方はご覧下さい。
>>参考記事: 「【まとめ】Spanning tree 仕様から検証結果の記事をまとめました!」
その他L2機能設計
上記以外にL2設計(Storm Control,UDLD,SPAN等)の設計方針、設定値、設定値の根拠を記載します。
L3設計
以下よりL3テクノロジー関連の設計を記載します。
※保守運用時に実施する新規ネットワーク機器の増設時に再設計/再検討がないように設計ポリシーを決めましょう。
IPアドレス設計
IPアドレスの採番方針、用途を定義します。
※各IPアドレスの利用端末は別紙_IPアドレス管理表を作成し管理しましょう。
- IPアドレスもVLANと同様で、用途毎にレンジを予約しましょう。
- 参考:IPアドレスの数値とVLANの番号に統一性を持たせると管理しやすいです。(例えばIPアドレスの第3オクテットとVLAN番号を合わせる等)
ルーティングプロトコル設計
ルーティング設計(OSPF,EIGRP,BGP等)の設計方針、設定値、設定値の根拠を記載します。
※各ネットワーク機器の設定は別紙_パラメータシートを作成し管理しましょう。
- ルーティングプロトコルの選定理由も明記しましょう。(例>キャリア網の仕様により〜)
- 再配布する場合は経路ループ対策(再配布制御)を実施しましょう。
- 再配布制御が必要となる理由とループ対策の実装方法(経路フィルター, tagなど)を分かりやすく図で纏めましょう。
OSPFに関する記事は以下に纏めておりますので、ご興味のある方はご覧下さい。
>>参考記事: 「【まとめ】OSPF 仕様から検証結果の記事をまとめました!」
無線設計
無線設計(SSID,無線LAN規格,ローミング,チャネル,電源供給等)の設計方針、設定値、設定値の根拠を記載します。
※各無線機器の設定は別紙_パラメータシートを作成し管理しましょう。
また、アクセスポイントを設置する場所は別紙_フロア図を作成し管理しましょう。
無線LAN設計について詳しく把握されたい方は、以下の記事をご参照ください。
>>参考記事: 「無線LANのトラブルを少なく!提案・基本設計時に考慮すべきこと!」
セキュリティ設計
セキュリティ設計(ファイアフォール,IPS,IDS,パスワード設計,アクセスリスト,各ネットワーク機器へのアクセス[リモートアクセス・コンソールアクセス等]の設計方針、設定値、設定値の根拠を記載します。
※各無線機器の設定は別紙_パラメータシートを作成し管理しましょう。
Qos設計
QoS設計(QoS適用箇所、マーキング、キューイング、輻輳回避など等)の設計方針、設定値、設定値の根拠を記載します。
その他L3機能設計
上記以外にL3設計(NAT,IP SLA,IPsec,DMVPN等)の設計方針、設定値、設定値の根拠を記載します。
>>参考記事: 「【無料】Cisco社のリモートラボ(Cisco DevNet)について」
>>参考記事: 「【無料】Juniper社のリモートラボ(vLabs)について」
可用性設計
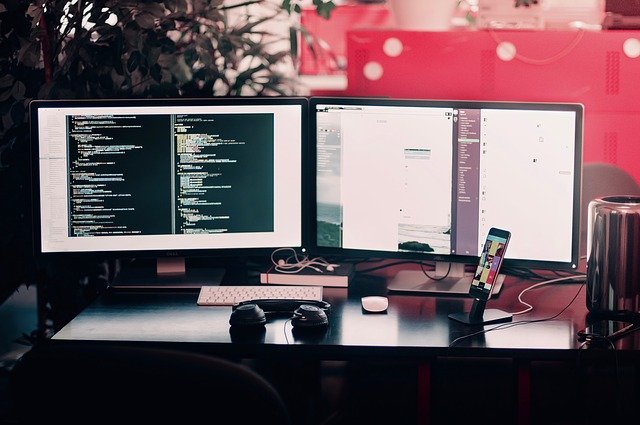
設計方針
可用性設計の大方針を定義します。
物理 冗長化設計
物理要素(拠点・回線・電源・機器・モジュール)に関する冗長化設計及び切替手法を記載します。
論理 冗長化設計
論理要素(リンクアグリゲーション・ルーティング)に関する冗長化設計(HSRP,VRRP,LACP,PAGP)及び切替手法を記載します。
障害設計

設計方針
障害設計の大方針を定義します。
正常時 通信経路設計
ネットワーク正常時の通信経路を定義します。
障害時 通信経路設計
ネットワーク障害時の通信経路・通信断時間を障害箇所毎に定義します。
復旧時 通信経路設計
ネットワーク復旧時の通信経路・通信断時間を定義します。
業務でよく利用するshowコマンド等を以下に纏めております。
ご興味のある方はご覧ください!
>>参考記事: 「【Juniper】業務で役立つshow、clear、requestコマンドを紹介!」
>>参考記事: 「【Cisco】業務で役立つOSPFのshow, debugコマンドを紹介!」
>>参考記事: 「【Cisco】業務で役立つBGPのshow, debugコマンドを紹介!」
拡張設計

設計方針
拡張設計の大方針を定義します。
物理 拡張設計
物理要素(拠点・回線・機器・モジュール)の拡張可能本数・台数を記載します。
論理 拡張設計
論理要素(VLAN数・経路数・Macアドレス数等)の拡張可能本数・台数を記載します。
保守運用設計

設計方針
保守設計の大方針を定義します。
監視設計
監視対象・監視手法・監視項目を記載します。
ログ設計
ログ取得機器・ログ取得項目・世代管理方式を記載します。
NTP設計
時刻同期先のサーバ指定、NTP関連設定値を記載します。
パケットキャプチャー設計
パケットキャプチャーの方式・取得内容・キャプチャーファイルの保管方式を記載します。
保守設計
保守対象一覧
保守機器を定義します。
構成管理設計
構成管理資料の定義、各資料の管理方法・更新フローを記載します。
障害対応設計
障害時の対応窓口・体制図・障害対応フローをを記載します。
Appendix
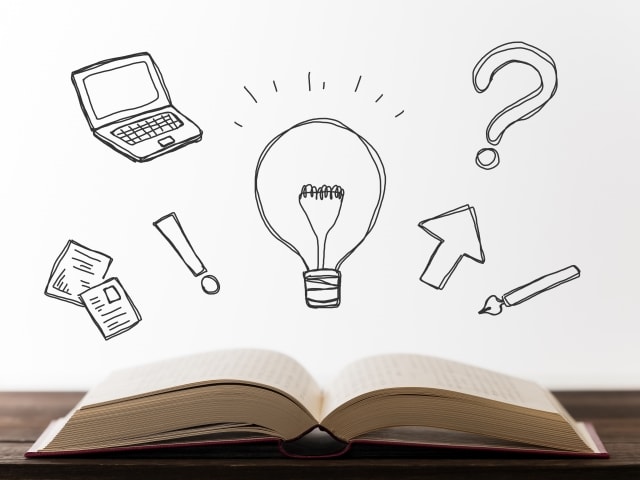
機器諸元
導入機器の情報(メーカ名、型番、重さ、大きさ、消費電力)を記載します。
まとめ

最後までお読み頂きましてありがとうございます。
私がネットワークエンジニアとして初心の時に以下の参考書にて設計スキルを身につけました。
非常に良本ですので、よりネットワーク設計スキルを高めたい方は一度ご覧ください!